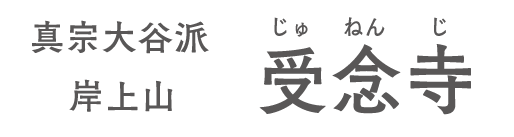私たちには、楽しい時を過ごしたいと思っていても、老いや病、死は避けようもなく襲いかかります。また家庭や社会、国同士など様々なレベルで争いが起こります。身近な間柄でも、言葉が相手を傷つけ、また傷つけられるということもあります。
別れの悲しみ、人への憎しみ、求めても得られない苦悩・・・人間として生きていくならば、誰もがぶつかる問題があります。それは時に人生を根本から揺るがし、自分の生きる道を見失うということもあります。そのような事態に、私たちはどのように向き合えば良いのでしょうか。
そんな苦悩の中にあっても、その苦悩からの問いかけに応えつつ、人生を輝かせ続ける道を歩んだ人物のことを「仏陀(ぶつだ)」(buddha, ブッダ)といいます。だから「仏陀になる」(成仏)ということは、特別な人の特別な境地ではなく、死後のことでもなく、誰もがもつ苦悩を乗り越え、自分が自分として満足に生き、自分の”いのち”を生命が尽きるまで燃やし尽くすことができる人になることなのです。
だから立場や境遇はそれぞれ違っても、そのさまざまな立場や境遇を超えて、仏陀のもとに、仏陀の教え(法, dharma, ダルマ)を聞こうと人が集まったのです。そのように、立場や境遇に関わらず、一人の人間として、苦悩を共に乗り越えていこうと心を一つにして歩む者たちを「僧伽」(saṃgha, サンガ)といいます。だからお寺は僧伽である、ということができると思います。
私たちはどのようないのちを生きているのか。どう生きることが、ほんとうにいのちを輝かせることになるのか。亡き人のいのちをどのように見れば、ほんとうにいのちの尊さを見ることになるのか。人と人との心がほんとうに響き合うとはどういうことか。
そういうことは日頃の「思い」の中から確かめることは難しいのです。なぜなら「思い」はいつも自分中心で、むしろ「思い」によって狭い世界に閉じ籠もり、行き詰まっていくからです。仏陀の智慧によって自分自身が問い返され、「思い」が破られたとき、自分自身が照らし出され、広い世界が開かれるということがあります。
自らの苦しみや悲しみを機縁として、自他のいのちを深く見つめ、人間として「生きること」を学ぶ。それが仏教であり、その教えを学ぶ場を開くことがお寺の役割であるといえます。